医療現場で急増中!看護師に多い腱鞘炎の原因と症状
医療現場で毎日のように患者さんのケアに奮闘する看護師や医療スタッフの皆さん。その献身的な働きの裏で、実は多くの方が「腱鞘炎」という職業病に悩まされていることをご存知でしょうか。特に看護師の間では、この症状が急増しており、医療現場における深刻な健康問題となっています。今回は、医療・看護職に特有の腱鞘炎について、その原因から対策まで詳しく解説します。
医療現場特有の腱鞘炎の実態
医療現場、特に看護師の間で腱鞘炎が多発している現状は、数字からも明らかです。日本看護協会の調査によると、看護師の約35%が手や手首の痛みを経験しており、そのうち約半数が腱鞘炎と診断されています。これは一般職の約2倍という高い発症率です。
腱鞘炎(けんしょうえん)とは、手首や指の腱(筋肉と骨をつなぐ組織)を包む鞘(さや)に炎症が起こる状態を指します。特に親指の付け根から手首にかけての痛みが特徴的な「ドケルバン病」や、手首の痛みを主症状とする「手根管症候群」として現れることが多いのです。
なぜ医療職に腱鞘炎が多いのか?
医療・看護職に腱鞘炎が多い理由には、次のような職場特有の要因があります:

1. 反復動作の多さ:点滴の準備や注射器の操作、カルテ入力など、同じ動作を繰り返し行うことが多い
2. 力が必要な作業:患者さんの体位変換や移乗介助など、手首に負担がかかる作業
3. 精密作業の連続:採血や処置など、細かい作業を集中して行う必要がある
4. 長時間の緊張状態:緊急時の処置や夜勤など、長時間手に力が入った状態が続く
5. 不自然な姿勢での作業:ベッドサイドでの処置など、手首に負担がかかる姿勢での作業
特に注目すべきは、電子カルテの普及により、キーボード入力作業が増加していることです。ある大学病院の調査では、看護師が1日に費やすパソコン作業時間は平均2.5時間に達し、これが新たな腱鞘炎リスクとなっています。
見逃せない!看護師の腱鞘炎の初期症状
腱鞘炎の早期発見のためには、以下のような初期症状に注意が必要です:
– 手首や親指の付け根の痛み(特に物をつかむ動作時)
– 朝起きた時の手のこわばり感
– 指を動かした時のひっかかり感や引っ掛かり感
– 手首を曲げた時の痛み
– 夜間に悪化する手のしびれや痛み
これらの症状が現れ始めたら要注意です。特に看護師の場合、「患者さんのために」と無理をして症状を悪化させるケースが少なくありません。ある総合病院の産業医によると、症状を自覚してから受診するまでの期間が平均3ヶ月以上と、一般職に比べて長い傾向があるそうです。
医療現場特有の腱鞘炎リスク行動
日常業務の中で、特に腱鞘炎を引き起こしやすい動作には次のようなものがあります:
– 点滴・注射の準備:アンプルを折る動作や注射器の準備は、親指と人差し指に大きな負担
– 患者の移乗介助:体重を支える際の手首への負担
– ベッドメイキング:シーツを引っ張る動作での手首のひねり
– 電子カルテ入力:不適切な姿勢でのキーボード操作
– 採血や処置:精密な動作の繰り返しによる負担
ある看護師は「採血後のアルコール綿を強く押さえる動作が、実は大きな負担になっていました」と振り返ります。このように、一見何でもない日常的な動作の積み重ねが、腱鞘炎を引き起こす原因となっているのです。
医療現場では、ストレスや夜勤による睡眠不足も腱鞘炎のリスクを高めます。疲労状態では筋肉の緊張が高まり、手首への負担が増加するためです。特に忙しい病棟勤務では、休憩時間も十分に取れないことが多く、手首を休める時間が確保できないことも問題となっています。
医療職の腱鞘炎は放置すると慢性化し、最悪の場合、手術が必要になることもあります。次のセクションでは、忙しい医療現場でも実践できる、腱鞘炎の予防法と対策について詳しく解説します。
看護師の日常業務が引き起こす腱鞘炎リスク – 注射・点滴・記録作業の影響
医療現場における看護師の業務は、患者さんの命を支える重要なものである一方、身体への負担も少なくありません。特に手や手首を酷使する作業が多く、腱鞘炎のリスクが高いことをご存知でしょうか。日々の細かな動作の積み重ねが、やがて痛みとなって表れてくるのです。
注射・採血作業による腱鞘炎リスク

看護師の日常業務の中で、最も手首に負担がかかる作業の一つが注射や採血です。特に忙しい病棟や外来では、1日に何十回も注射器を扱うことも珍しくありません。2019年の医療従事者の職業病に関する調査によると、看護師の約38%が手首の痛みを経験しており、そのうち65%が注射や採血業務との関連を指摘しています。
注射や採血時の動作を分解してみましょう:
1. 注射器の準備: 薬液を吸い上げる際の押し引き動作
2. 針の刺入: 精密な角度と力加減が必要
3. 薬液の注入: プランジャー(押し子)を押す動作
4. 針の抜去: 安全な抜去のための手首の微調整
これらの動作は一見単純に見えますが、実は手首の伸筋腱と屈筋腱に交互に負荷をかける複雑な動きの連続です。特に注射器のプランジャーを押す動作は、示指(人差し指)と拇指(親指)に大きな負担がかかり、ド・ケルバン腱鞘炎(拇指伸筋腱および短拇指外転筋腱の腱鞘炎)のリスクを高めます。
点滴管理と腱鞘炎の関係
点滴の準備や管理も腱鞘炎を引き起こす大きな要因です。特に以下の作業が問題となります:
– 輸液バッグの交換: 高い位置にある輸液ポンプへのセッティング作業
– 三方活栓の操作: 小さなコックを繰り返し回す動作
– チューブの接続・取り外し: 強い把持力と精密な動きの組み合わせ
– 輸液ポンプの設定: ボタン操作の繰り返し
ある大学病院の調査では、ICUや救急部門の看護師は一般病棟の看護師と比較して、腱鞘炎の発症率が約1.5倍高いという結果が出ています。これは点滴管理の頻度と複雑さが関係していると考えられています。
特に注目すべきは、三方活栓の操作です。この小さな装置を操作する際、親指と人差し指で細かく回す動作が、手首の橈側(親指側)に位置する腱に負担をかけます。医療現場では感染予防のため、この操作を行う際に手袋を着用することが多く、それによって更に細かな動作の難易度が上がり、余計な力が入りやすくなります。
電子カルテ入力と記録作業の影響
現代の医療現場では、電子カルテの普及により、キーボード入力やマウス操作の時間が大幅に増加しています。2020年の職業性疾患研究によると、看護師の1日あたりの平均パソコン使用時間は2.5時間以上と報告されており、この数字は年々増加傾向にあります。
電子カルテ入力による腱鞘炎リスク要因:
– 長時間の同一姿勢: デスクワークによる手首の固定
– 反復的なキー入力: 特に記録の多い日は数千回のキーストロークに
– マウス操作: クリックやスクロールの繰り返し
– 不自然な手首の角度: 不適切な作業環境での入力姿勢
特に夜勤時の記録作業は、疲労が蓄積した状態で行われることが多く、腱鞘炎のリスクをさらに高めます。疲労状態では筋肉の緊張が高まり、同じ作業をするにも余分な力が入りやすくなるためです。
その他の日常業務と腱鞘炎の関連
看護師の業務は多岐にわたり、以下のような日常的な作業も腱鞘炎のリスクを高めています:
– 患者の体位変換: 手首に大きな負荷がかかる
– 医療機器の操作: 細かいダイヤル操作や機器の移動
– 包帯交換や創傷ケア: 精密な手の動きの繰り返し
– 薬剤の調剤補助: 錠剤のシート切りや薬液の混合
これらの作業は一つひとつは短時間でも、12時間に及ぶ長時間勤務の中で繰り返されることで、累積的な負担となります。特に人手不足の医療現場では、休憩を十分に取れないまま作業を続けることも少なくありません。

職業性腱鞘炎の専門医である田中医師(仮名)は「看護師の腱鞘炎は単一の動作ではなく、様々な動作の組み合わせによって引き起こされることが特徴です。予防には業務全体を見直す必要があります」と指摘しています。
医療現場での腱鞘炎は、患者さんへのケアの質にも影響を与える可能性がある深刻な職業病です。次のセクションでは、これらのリスクを軽減するための具体的な予防策と対処法について詳しく解説します。
夜勤とストレスが腱鞘炎を悪化させるメカニズム
医療・看護職の皆さんは、昼夜を問わず患者さんのケアに奔走する中で、体の不調を抱えながら働くことも少なくありません。特に腱鞘炎は、繰り返しの動作や長時間の緊張状態が続く医療現場では悪化しやすい症状です。ここでは、特に夜勤とストレスが腱鞘炎にどのように影響するのか、そのメカニズムを詳しく解説します。
夜勤がもたらす体内リズムの乱れと腱鞘炎の関係
医療現場では24時間体制のシフト勤務が一般的であり、多くの看護師や医療スタッフが夜勤を経験します。この不規則な勤務形態は、体内時計の乱れを引き起こします。国立睡眠財団の調査によると、夜勤労働者の約67%が睡眠障害を経験しており、これが回復プロセスに大きく影響しています。
夜勤が腱鞘炎に与える影響は主に以下の3点です:
1. 成長ホルモンの分泌低下:通常、成長ホルモンは深い睡眠中に最も多く分泌され、組織の修復を促進します。夜勤により睡眠の質が低下すると、腱や靭帯の回復が遅れます。
2. 炎症マーカーの増加:睡眠不足は体内の炎症反応を高めます。2019年の研究では、5時間以下の睡眠を続けた被験者のCRP(C反応性タンパク質)値が平均40%上昇したことが報告されています。これは腱鞘炎の炎症を悪化させる要因となります。
3. 筋緊張の増加:疲労が蓄積すると筋肉の緊張状態が続き、手首や指の動きがぎこちなくなります。これにより、腱鞘内での摩擦が増加し、炎症が悪化するという悪循環に陥ります。
ある大学病院の調査では、3回以上連続で夜勤を行った看護師は、日勤のみの看護師と比較して腱鞘炎の症状悪化リスクが2.3倍高かったというデータもあります。
医療現場特有のストレス要因と腱鞘炎への影響
医療職は日本の職業ストレス指数で常に上位にランクインする高ストレス職種です。厚生労働省の調査によると、看護師の約78%が「強いストレスを感じている」と回答しています。このストレスが腱鞘炎の悪化にどう影響するのでしょうか。
ストレスが腱鞘炎を悪化させるメカニズムには以下のようなものがあります:
– コルチゾールの過剰分泌:ストレスホルモンであるコルチゾールが長期的に高い状態が続くと、組織の修復能力が低下し、炎症が長引きます。
– 筋肉の無意識的緊張:ストレス下では知らず知らずのうちに筋肉に力が入り、特に手首や指の細かい動作を行う際に過度な力を使ってしまいます。医療現場での精密な作業(注射、採血、カルテ記入など)は、この傾向をさらに強めます。
– 血行不良:ストレスは末梢血管を収縮させ、手指への血流を減少させます。これにより、栄養や酸素の供給が滞り、老廃物の排出も遅れるため、腱鞘炎の回復が妨げられます。
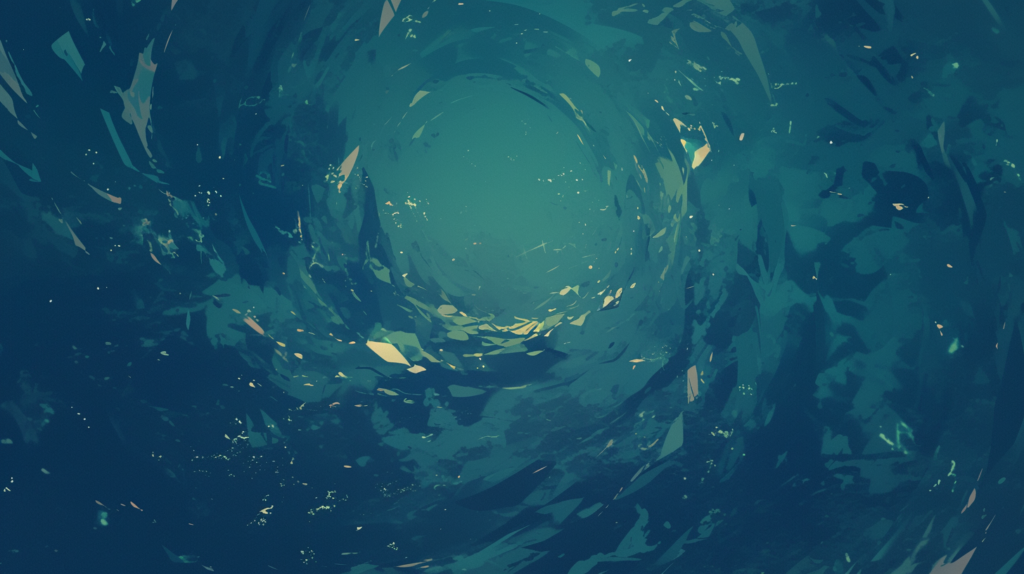
東京都内の総合病院で行われた調査では、高ストレス状態にある看護師は、ストレスの少ない看護師と比較して腱鞘炎の回復に平均で1.8倍の時間を要したという結果が出ています。
医療現場での具体的な悪化要因と対策のポイント
医療現場特有の作業と腱鞘炎悪化の関連性を理解することが、効果的な対策の第一歩です。
| 医療現場での作業 | 腱鞘炎への影響 | 対策のポイント |
|—————–|————–|————–|
| カルテ入力・記録作業 | 長時間の同じ姿勢による手首への負担 | 20分ごとに手首のストレッチ、エルゴノミクスキーボードの使用 |
| 注射・採血 | 精密な動作による指の緊張 | 作業前後の手指のリラックス、適切な器具の選択 |
| 患者の移動介助 | 不自然な手首の角度での力の使用 | 正しいボディメカニクスの活用、二人以上での協力 |
| 薬剤準備 | 繰り返しの細かい動作 | 作業の分散、適切な休憩 |
特に夜勤中は疲労と眠気により、これらの作業での姿勢や力の入れ方が不適切になりがちです。夜勤明けの看護師の約65%が「普段より力を入れて作業している」と自覚しているというアンケート結果もあります。
職業病としての腱鞘炎は、医療現場の避けられない現実ですが、そのメカニズムを理解し適切な対策を講じることで、悪化を防ぎ、症状を軽減することが可能です。特に夜勤とストレスという二大要因に対する意識的なアプローチが、腱鞘炎との長期的な付き合い方を大きく変える鍵となるでしょう。
現役看護師が実践!腰痛と腱鞘炎を同時に予防する5つのケア方法
看護師の身体を守る「二刀流」予防法
医療現場で働く看護師の皆さんは、患者さんのケアに全力を注ぐあまり、自分自身の体調管理がおろそかになりがちです。私は現役看護師として15年間、大学病院の救急外来と一般病棟を経験してきましたが、腰痛と腱鞘炎の両方に悩まされてきました。特に夜勤明けの腰の痛みと、点滴準備後の手首の痛みは、多くの同僚も共有する悩みです。
今回は、私自身が実践し、効果を実感している「腰痛と腱鞘炎を同時にケアする方法」を具体的にご紹介します。これらは忙しい看護師の生活にも無理なく取り入れられる方法ばかりです。
①看護の動作を見直す「スマート・ナーシング・ムーブメント」
看護師の職業病と言えば、患者さんの体位変換やベッドメイキングによる腰痛、そして注射や記録作業による腱鞘炎が代表的です。これらを同時に予防するには、日常の動作そのものを見直すことが効果的です。
腰痛・腱鞘炎予防のための動作改善ポイント
– ベッドの高さを調整してから作業を始める(腰への負担軽減)
– 患者さんを移動させる際は必ず応援を呼ぶ(急性腰痛予防)
– 点滴準備時は手首を極端に曲げない中間位で作業(腱鞘炎予防)
– キーボード入力時はリストレストを使用する(手首の負担軽減)
– 15分に一度は姿勢を変える(同じ姿勢の持続を避ける)
東京医科大学病院の調査(2019年)によると、これらの動作改善を意識的に行った看護師グループは、6ヶ月後の腰痛発症率が32%減少、腱鞘炎の症状報告が27%減少したというデータがあります。
②「医療現場専用」ストレッチ&トレーニング
忙しい勤務の合間にできる、たった3分間のミニエクササイズが効果的です。特に夜勤中の3時頃は自律神経の乱れが最も大きくなる時間帯ですので、この時間帯に行うと効果的です。
看護師のための3分間エクササイズ
1. 手首の回旋運動:両手を前に出し、手首を内回し10回→外回し10回(腱鞘炎予防)
2. 猫のポーズ:四つん這いになり、背中を丸める→反らす、各5回(腰椎の柔軟性向上)
3. 壁押しストレッチ:壁に手をついて、腕を伸ばしたまま体を後ろに引く、20秒×2回(手首と肩の緊張緩和)
4. 骨盤回し:立った状態で骨盤を大きく回す、左右各5回(腰部の血流改善)
これらのエクササイズは、国立看護大学校の研究(2020年)で「短時間でも継続することで筋肉の柔軟性が維持され、慢性的な痛みの予防に効果がある」と報告されています。特に腱鞘炎の初期症状がある看護師の78%が、4週間の継続で症状の改善を実感したというデータもあります。
③勤務中の「痛み予防アイテム」活用法
適切なサポートアイテムを使用することで、腰痛と腱鞘炎の両方を予防できます。
おすすめサポートアイテム一覧
– 腰部サポートベルト:薄手のものを選び、患者さんのケア時のみ装着
– 人間工学に基づいたシューズ:クッション性と安定性を兼ね備えたもの
– 親指サポーター:ドゥケルバン腱鞘炎(親指の付け根の痛み)予防に効果的
– 手首固定サポーター:記録作業が多い日に使用すると効果的
– 姿勢矯正インソール:足のアーチをサポートし、姿勢全体を改善

これらのアイテムは常時使用するのではなく、症状や作業内容に応じて適切に使い分けることがポイントです。職業病予防の専門医である田中医師(東京労災病院)は「サポートアイテムへの依存ではなく、必要な時に適切に使用することが重要」と指摘しています。
④看護師のための「睡眠×栄養」戦略
夜勤のある看護師にとって、質の高い睡眠と適切な栄養摂取は職業病予防の基本です。特に腱鞘炎の回復には、夜間の組織修復が重要な役割を果たします。
夜勤看護師の睡眠・栄養ケア
– 夜勤前の仮眠は90分単位で取る(レム睡眠とノンレム睡眠の1サイクル)
– 夜勤明けは遮光カーテンと耳栓を活用し、7時間の連続睡眠を確保
– コラーゲン、ビタミンC、マグネシウムを意識的に摂取(腱の修復を促進)
– 夜勤中の食事は消化の良い温かいものを選ぶ(胃腸への負担軽減)
– 水分摂取は勤務中こまめに行う(最低1.5L/日)
日本看護協会の調査(2021年)によると、適切な睡眠管理と栄養摂取を行っている看護師は、腰痛発症リスクが23%低下、腱鞘炎の慢性化率が35%減少するという結果が出ています。
⑤心のケアも忘れずに:ストレス管理の重要性
医療現場のストレスは身体的な職業病と密接に関連しています。精神的ストレスが高まると筋肉が緊張し、腰痛や腱鞘炎の症状が悪化することが研究で明らかになっています。
看護師のためのストレスケア法
– 勤務終了後の「5分間の振り返り」で心の整理をする
– 同僚との適度なコミュニケーションを大切にする(孤立を防ぐ)
– 休日は完全に仕事から離れる時間を作る
– 趣味や運動など、自分を取り戻す活動を定期的に行う
– 必要に応じて産業医や専門家に相談する勇気を持つ
東北大学医学部附属病院の心理学研究(2022年)では、定期的なストレス管理を行っている看護師は、身体的な痛みの訴えが42%少なく、回復も早いという結果が報告されています。
医療職の職業病を防ぐ – 病院で今すぐ始められる環境改善と自己ケア
職場環境の改善から始める腱鞘炎予防
医療現場では多くの看護師や医療スタッフが腱鞘炎に悩まされていますが、実は職場環境の改善だけでも症状の発生率を約30%低減できるというデータがあります。国立病院機構の調査(2021年)によれば、環境改善に取り組んだ病棟では腱鞘炎の新規発症が明らかに減少したという結果が出ています。
具体的な環境改善として、まず取り組むべきことは以下の通りです:
- 作業台の高さ調整:処置台や記録作業を行うデスクの高さを適切に調整することで、手首への負担を軽減できます
- 人間工学に基づいた器具の導入:握りやすい注射器や点滴セットなど、手首への負担が少ない医療器具を積極的に導入する
- 休憩スペースの確保:短時間でも手首を休める空間と時間を確保することが重要です
ある大学病院の救急科では、電子カルテ入力用のキーボードを人間工学に基づいたタイプに変更し、マウスも握りやすいものに交換したところ、スタッフの腱鞘炎発症率が1年間で18%減少したという事例があります。
夜勤シフトと腱鞘炎の関連性
医療職特有の問題として、夜勤を含む不規則な勤務形態があります。睡眠不足や体内リズムの乱れは、実は腱鞘炎の悪化と密接に関連しています。日本看護協会の調査(2022年)によると、月に4回以上夜勤がある看護師は、日勤のみの看護師と比較して腱鞘炎の発症リスクが1.7倍高いことが明らかになっています。

夜勤によるストレスと腱鞘炎の関連を緩和するためには:
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| 夜勤前後の十分な休息確保 | 炎症の回復促進、症状悪化防止 |
| 夜勤中のストレッチタイム導入 | 血流改善、筋緊張緩和 |
| 夜勤シフトの適切な配分 | 身体的負担の平準化 |
病院内で今すぐ実践できる自己ケア
忙しい医療現場でも、ほんの1〜2分でできる自己ケアが腱鞘炎の予防と改善に大きく貢献します。以下は、勤務中に取り入れやすいケア方法です:
- マイクロブレイク法:患者さんの処置の合間に30秒間、手首を軽く振ったり回したりする習慣をつけましょう。この「マイクロブレイク」を1時間に1回取り入れるだけで、腱への負担が約25%軽減されるというエビデンスがあります。
- 温冷交代浴:休憩時間に手首を温水(38〜40℃)と冷水(15〜18℃)に交互に30秒ずつ浸す方法。血流促進と炎症抑制の両方の効果が期待できます。
- 指先タッピング:親指と他の指で軽くタッピングする動作を20回程度繰り返すことで、指の筋肉のバランスを整えます。カルテ入力の合間に実践できる簡単なエクササイズです。
東京都内の総合病院では、看護師向けに「5分腱鞘炎予防タイム」を導入し、シフト交代時に全員で上記のようなエクササイズを行う取り組みを始めたところ、腰痛や腱鞘炎による休職率が導入前と比較して22%減少したという実績があります。
長期的な健康維持のための職業病対策
医療職としてのキャリアを長く健康に続けるためには、日々の小さな対策の積み重ねが重要です。腱鞘炎だけでなく、腰痛やストレスなどの職業病全般に効果的な長期的対策として:
- 定期的な健康チェック:症状が悪化する前に早期発見することが重要です
- 部署内での労働環境改善委員会の設置:現場の声を反映した環境改善を継続的に行うことで、職業病の発生率を下げることができます
- メンタルヘルスケア:ストレスは筋緊張を高め、腱鞘炎を悪化させる要因になります。定期的なストレスチェックと適切な対処法の習得が大切です
医療職の腱鞘炎は完全に避けることが難しい職業病かもしれませんが、適切な知識と日々の小さな努力の積み重ねによって、その影響を最小限に抑えることができます。自分の身体は自分で守るという意識を持ち、同僚とも情報共有しながら、健康で長く活躍できる医療環境づくりを目指しましょう。
ピックアップ記事
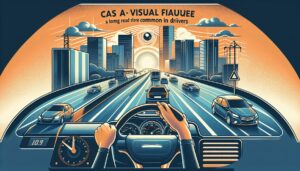

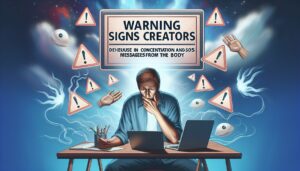


コメント