デスクワークによる身体への影響と代表的な職業病
現代のオフィスワーカーが長時間同じ姿勢でパソコン作業を続けることで、様々な身体の不調が引き起こされています。厚生労働省の調査によると、デスクワーク従事者の約70%が何らかの身体的不調を感じているというデータもあります。ここでは、デスクワークによって引き起こされる主な職業病とその症状について詳しく見ていきましょう。
肩こり・首の痛み(テクノネック症候群)
デスクワーカーの約80%が経験するといわれる「肩こり・首の痛み」。通称「テクノネック症候群」と呼ばれるこの症状は、長時間のパソコン作業によって首が前傾姿勢になることで引き起こされます。
主な症状
- 首から肩にかけての強い張り感
- 頭痛や吐き気を伴うケース
- 重度の場合、腕のしびれや痛みが発生

2023年に東京都内のIT企業1,000名を対象にした調査では、在宅勤務の増加に伴い、肩こりの訴えが2019年比で約1.5倍に増加しているというデータもあります。特に注目すべきは、20代の若年層での増加率が高いという点です。
腰痛(VDT症候群)
オフィスワーカーの職業病として最もポピュラーな「腰痛」。特にデスクワークに関連する腰痛は「VDT症候群」の一症状として知られています。
腰痛が発生する主な原因
- 長時間の座位姿勢による骨盤の歪み
- 筋肉の緊張と血行不良
- 不適切な椅子やデスクの高さ
日本整形外科学会の報告によると、職業性腰痛の約40%がデスクワークに起因するものだとされています。特に注目すべき点は、一般的に思われている「重いものを持つ仕事」よりも、「同じ姿勢を長時間続ける仕事」の方が腰痛リスクが高いというデータです。
手首のトラブル(腱鞘炎・マウス肘)
キーボードやマウスを使い続けることによる「手首のトラブル」も代表的な職業病です。
手首に関する主な症状
| 症状名 | 主な症状 | 発症率(オフィスワーカー) |
|---|---|---|
| 腱鞘炎 | 手首の痛みやはれ、指の曲げ伸ばしの制限 | 約30% |
| マウス肘 | 肘の外側の痛み、手首を回す動きでの痛み | 約25% |
| 手根管症候群 | 親指〜中指のしびれ、握力低下 | 約15% |
特に「手根管症候群」は早期発見・早期治療が重要で、放置すると手術が必要になるケースもあります。米国労働統計局のデータによれば、オフィスワーカーの休職理由の第3位が手首のトラブルとなっており、近年のスマートフォン普及によってさらに症状が悪化するケースも報告されています。
目の疲れ(ドライアイ・ブルーライト障害)
デジタルデバイスを長時間見続けることによる「目の疲れ」も深刻な問題です。

主な症状と特徴
- ドライアイ: 目の乾燥感、異物感、疲労感
- ブルーライト障害: 目の充血、かすみ、頭痛
- CVS(コンピュータービジョン症候群): 目の焦点合わせの困難、視力低下
日本眼科医会の調査では、デスクワーカーの約65%が目の疲れを感じており、その中の約40%が「仕事の効率に影響がある」と回答しています。特に1日のスクリーン使用時間が7時間を超えると、これらの症状が急激に増加するというデータもあります。
近年では在宅勤務の増加によって、オフィスよりも照明環境が整っていない自宅での長時間作業が増え、目の疲労はさらに深刻化しているといえるでしょう。
これらの身体的な職業病は、単に個人の不調というだけでなく、業務効率の低下や休職といった社会的・経済的な損失にもつながります。次の章では、このような身体的な問題に加えて、オフィスワーカーに多い精神的なストレスや心の健康問題について探っていきます。
オフィスワーカーに多い精神的ストレスと心の健康問題
現代のオフィス環境では、身体的な問題だけでなく、精神的な健康問題も深刻化しています。厚生労働省の「労働者健康状況調査」によると、オフィスワーカーの約60%が「強いストレスを感じている」と回答しており、その数は年々増加傾向にあります。ここでは、オフィスワーカーに特徴的な精神的ストレスと心の健康問題について詳しく見ていきましょう。
燃え尽き症候群(バーンアウト)
長時間労働や高いプレッシャーが続くことで発症する「燃え尽き症候群」は、近年特に注目されている職業病です。
バーンアウトの主な特徴
- 極度の疲労感と意欲の喪失
- 仕事への冷笑的な態度
- 業務効率の著しい低下
- 無力感や達成感の欠如
日本産業カウンセラー協会の調査によると、特にIT業界や金融業界のオフィスワーカーにバーンアウトの発症率が高く、30代〜40代の中堅社員層で顕著に見られます。世界保健機関(WHO)は2019年に初めてバーンアウトを「職業現象」として正式に定義し、その重要性を国際的に認識しています。
テクノストレス
テクノストレスとは、ITツールやデジタル技術の急速な変化や複雑化によって引き起こされるストレス反応です。
テクノストレスの種類と症状
- テクノ不安: 新しいシステムや技術についていけない不安
- テクノ依存: メールやSNSを常にチェックせずにいられない依存
- テクノ過負荷: 膨大な情報量に圧倒される感覚

総務省の情報通信白書によると、日本のビジネスパーソンの約45%がテクノストレスを感じており、特にリモートワークへの急速な移行が進んだ2020年以降、その数値は顕著に上昇しています。
専門家によると、1日に処理するメール数が50通を超えると、テクノストレスのリスクが大幅に上昇するというデータもあります。現代のオフィスワーカーは平均して1日約85通のメールを処理しているとされ、多くの人がリスク圏内にいると言えるでしょう。
うつ病・適応障害
職場でのプレッシャーや人間関係の問題から発症する「うつ病」や「適応障害」もオフィスワーカーに多い精神疾患です。
オフィスワーカーの精神疾患の特徴
| 症状 | 主な特徴 | オフィスワーカーの発症率 |
|---|---|---|
| うつ病 | 持続的な憂うつ感、興味・喜びの喪失、睡眠障害 | 約10〜15% |
| 適応障害 | 特定のストレス因子による一時的な適応困難 | 約20% |
| 不安障害 | 過度の心配や恐怖、パニック発作 | 約12% |
興味深いのは、管理職とそれ以外の社員では発症パターンが異なるという点です。日本メンタルヘルス協会のデータによれば、管理職は「責任の重さ」や「成果への圧力」からうつ症状を発症しやすいのに対し、一般社員は「人間関係のストレス」や「評価への不安」が主な要因となるケースが多いようです。
睡眠障害(テクノ不眠)
デジタルデバイスの使用増加に伴い、「テクノ不眠」と呼ばれる睡眠障害も増加しています。
テクノ不眠の主な原因
- 夜間のブルーライト露出による睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌抑制
- 就寝前の仕事メールチェックによる脳の覚醒
- SNSやニュースのスクロールによる情報過多
日本睡眠学会の調査では、就寝前30分以内にデジタルデバイスを使用するオフィスワーカーは、そうでない人と比較して入眠に平均で約40分多くの時間を要することが分かっています。また、睡眠の質も低下し、日中のパフォーマンスに大きく影響します。
特に在宅勤務の増加によって仕事とプライベートの境界が曖昧になり、夜遅くまで仕事関連のデバイスを使用する「デジタル残業」が増えていることも、睡眠障害増加の一因と考えられています。
「休めない症候群」と有給休暇取得率の問題
日本のオフィスワーカーに特徴的な問題として、「休めない症候群」も挙げられます。有給休暇を取得しづらい職場文化や、休暇中でもメールをチェックせずにいられない心理的な圧力が、真の意味での「休息」を困難にしています。
厚生労働省の調査によると、日本の有給休暇取得率は約56.3%(2022年)で、先進国の中でも低い水準にあります。特にマネジメント層の取得率は約40%と更に低く、上司が休まない職場では部下も休みづらいという「連鎖」が生じています。

休息不足の慢性化は、単なる疲労感だけでなく、創造性の低下や判断力の鈍化、そして長期的には前述の様々な精神疾患のリスク要因となります。
これらの精神的な職業病は、身体的な症状と違って目に見えにくく、周囲から理解されづらい点が特徴です。次の章では、これらの身体的・精神的な職業病に対する効果的な予防策とオフィス環境の改善方法について探っていきます。
職業病の予防策とオフィス環境の改善方法
ここまで見てきたように、オフィスワーカーには様々な身体的・精神的な職業病のリスクがあります。しかし、適切な予防策と環境改善によって、これらのリスクを大幅に軽減することが可能です。ここでは、具体的な予防策とオフィス環境の改善方法について探っていきましょう。
エルゴノミクスに基づいたワークステーションの設計
「エルゴノミクス」とは、人間工学に基づく設計思想のことで、デスク環境を最適化することで身体的な職業病を予防します。
理想的なワークステーションの条件
- モニターの高さ: 目線がモニター上部と同じか、やや下になる位置
- キーボードの位置: 肘が90度に曲がる高さ
- 椅子の調整: 足が床にしっかりとついた状態で、腰がサポートされる
- 足置き: 必要に応じて足置きを使用し、血流を促進
産業医科大学の研究によると、エルゴノミクスに基づいたオフィス環境の改善により、肩こりや腰痛の訴えが約40%減少したというデータもあります。特に注目すべきは、これらの改善は比較的低コストで実現できる点です。
エルゴノミクス改善のコストパフォーマンス比較
| 改善策 | 予算感 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 人間工学椅子の導入 | 中〜高 | 腰痛・肩こり軽減(▲35%) |
| モニタースタンド | 低 | 首の痛み軽減(▲30%) |
| キーボード・マウスの改良 | 低〜中 | 手首の痛み軽減(▲45%) |
| 立ち座り両用デスク | 高 | 全身の不調軽減(▲50%) |
適切な休憩とストレッチの習慣化
長時間同じ姿勢を続けることは、多くの職業病の原因となります。定期的な休憩とストレッチを習慣化することで、これらのリスクを軽減できます。
効果的な休憩パターン
- 20-20-20ルール: 20分ごとに、20フィート(約6メートル)先を20秒見る(目の疲れ防止)
- ポモドーロ・テクニック: 25分の集中作業と5分の休憩を繰り返す
- マイクロブレイク: 1時間に1回、2分程度の小休憩と軽いストレッチ
東京大学大学院医学系研究科の調査によると、1時間に5分程度の休憩とストレッチを導入した企業では、筋骨格系の不調による休職が約30%減少したという結果も出ています。

オフィスでできる簡単ストレッチ
- 首回し: 首をゆっくり回して緊張をほぐす
- 肩すくめ: 肩を上げ下げして血行を促進
- 胸の開き: 両腕を後ろに引いて胸を開く
- 手首のストレッチ: 手首を様々な方向に曲げてほぐす
- 背伸び: 椅子に座ったまま背筋を伸ばし、腕を上に伸ばす
デジタルデトックスとテクノストレス対策
テクノストレスや精神的な職業病を予防するためには、適切なデジタルデトックスが重要です。
具体的なデジタルデトックス策
- 通知の制限: 不要な通知をオフにし、集中力を保護
- デジタルサンセット: 就寝前1〜2時間はデジタルデバイスを使用しない
- メールチェック時間の設定: 1日2〜3回の決まった時間にメールをチェック
- ブルーライトカットフィルター/メガネ: 夜間の光の質を調整
京都大学の実験では、メールチェックを1日3回に制限した参加者は、常時チェックしていた参加者と比較して、ストレスホルモン(コルチゾール)のレベルが約26%低かったというデータもあります。
職場のメンタルヘルス対策と組織文化の改善
職業病の予防には、個人の努力だけでなく、組織としての取り組みも不可欠です。
効果的な組織的取り組み
- メンタルヘルス研修: 管理職を含めた全社員への定期的な教育
- ストレスチェック: 法定のストレスチェックを活用した早期発見
- EAP(従業員支援プログラム): 専門家によるカウンセリングの提供
- フレックスタイム/リモートワーク: 柔軟な働き方による負担軽減
日本労働研究機構の調査によると、メンタルヘルス対策を積極的に行っている企業は、そうでない企業と比較して従業員の離職率が約20%低く、生産性が約15%高いというデータも報告されています。
「休める」組織文化の醸成
- 上層部からの休暇取得: リーダーが率先して休暇を取得する
- 休暇取得の評価: 休暇取得率を管理職の評価項目に入れる
- 代替要員の確保: 休暇中の業務をカバーする体制づくり
- 計画的な休暇設定: 年間を通じた休暇計画の策定
健康経営としての職業病対策

最近注目されている「健康経営」の考え方では、従業員の健康維持・増進は企業の持続的な成長に不可欠な投資と位置づけられています。
健康経営の具体的施策
- 健康増進プログラム: ウォーキングチャレンジなどの運動促進
- 栄養サポート: 健康的な社食やスナックの提供
- 睡眠改善セミナー: 質の高い睡眠についての教育
- 定期的な健康診断とフォローアップ: 早期発見・早期対応
経済産業省の「健康経営銘柄」に選定された企業の調査では、健康経営に取り組んだ企業の株価パフォーマンスは、TOPIX平均を約15%上回るという結果も出ています。これは、従業員の健康対策が単なるコストではなく、企業価値を高める投資であることを示しています。
職業病対策は、個人の努力と組織的な取り組みの両方が必要です。デスクワークによる身体的な不調、テクノストレスや精神的な問題に対して、予防的なアプローチを取ることで、オフィスワーカーはより健康的に、そして生産的に働くことができるでしょう。適切な対策を講じることで、職業病によるコストを削減し、従業員の幸福度と生産性を高めることが可能なのです。
ピックアップ記事

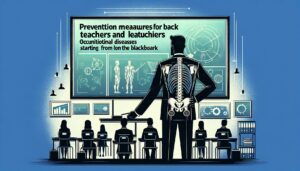

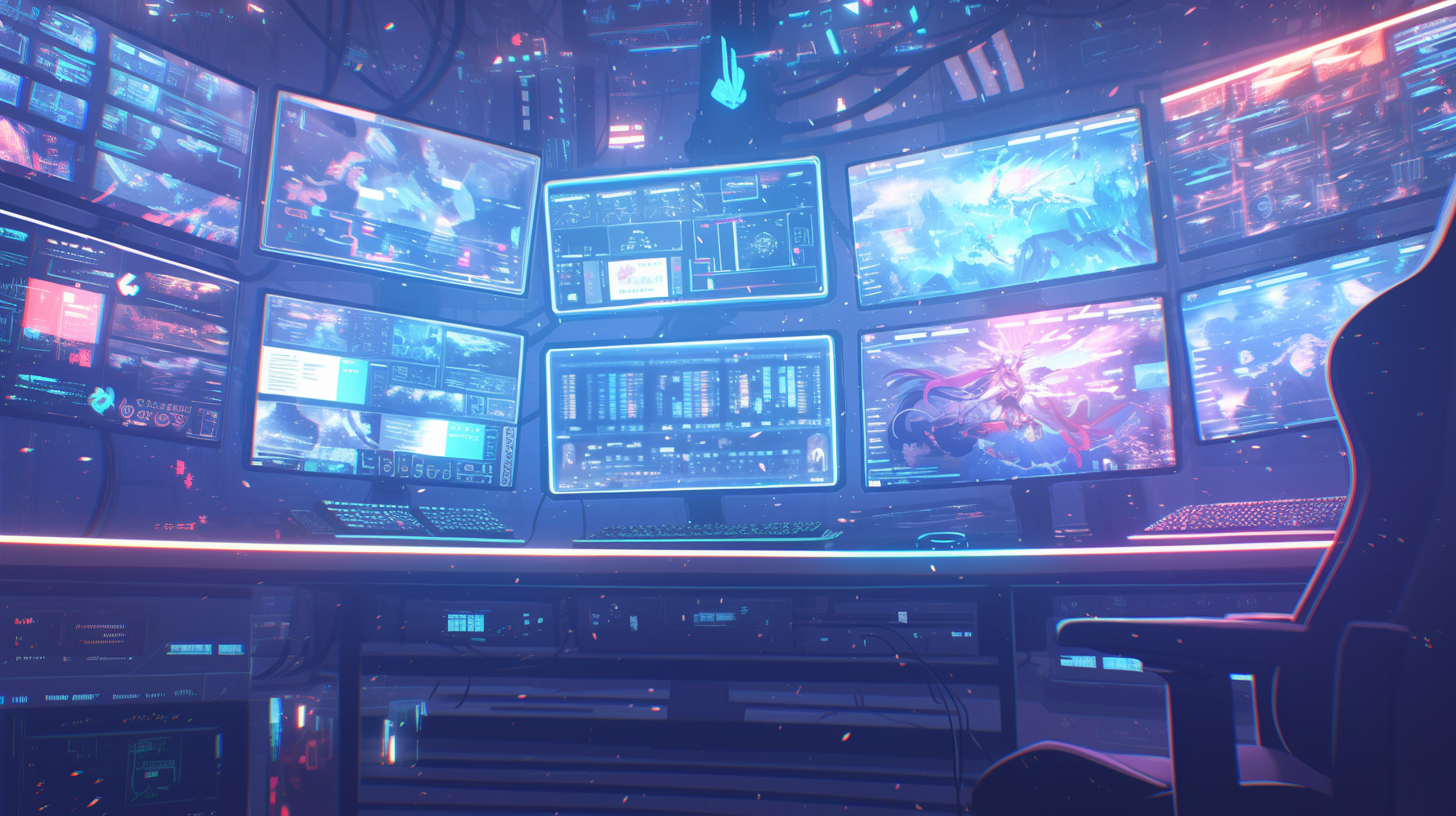

コメント