職業病の基本知識と定義
職業病とは、特定の職業に従事することによって引き起こされる健康障害のことを指します。日本では労働安全衛生法によって「業務上の疾病」として定義され、労働者災害補償保険法(労災保険)の対象となっています。職業病は単なる一般的な病気とは異なり、特定の職業環境や作業内容に直接関連して発症するという特徴があります。
職業病の歴史的背景
職業病の概念は古くからありましたが、産業革命以降、特に注目されるようになりました。日本では高度経済成長期に多くの職業病が社会問題化し、その結果として労働安全衛生法の整備が進みました。代表的な例として、1950年代から60年代にかけての四大公害病のうち、水俣病やイタイイタイ病などは職業病としての側面も持っていました。
職業病の法的位置づけ
日本の労働安全衛生法では、職業病は以下のように分類されています:
- 物理的因子による疾病:騒音性難聴、振動障害など
- 化学物質による疾病:有機溶剤中毒、じん肺など
- 生物学的因子による疾病:感染症、アレルギーなど
- 身体的負荷による疾病:腰痛、頸肩腕障害など
- 精神的ストレスによる疾病:うつ病、PTSD、過労死など

労災認定された場合は、治療費や休業補償など様々な保障を受けることができます。しかし、職業病の認定には因果関係の証明が必要となるケースが多く、認定までのハードルは決して低くないのが現状です。
職業病の現代的課題
現代社会における職業病の問題は、従来の製造業や建設業だけでなく、サービス業やIT業界にも広がっています。特に注目すべき現代的課題としては以下のようなものがあります:
テクノストレスと新しい職業病
デジタル技術の進展に伴い、いわゆる「テクノストレス」と呼ばれる新たな職業病が増加しています。長時間のパソコン作業によるドライアイや肩こり、スマートフォンの過度な使用による「テキストネック」など、情報化社会特有の健康問題が増えています。
厚生労働省の調査によれば、VDT作業(Visual Display Terminals、コンピュータ画面を見る作業)に関連した健康問題を抱える労働者は全体の約40%にも上るとされています。
精神的健康問題の増加
現代の職場ではメンタルヘルスの問題が深刻化しています。厚生労働省の「労働者健康状況調査」によれば、強いストレスを感じている労働者の割合は約60%に達しています。過重労働やパワーハラスメントなどの問題が精神疾患を引き起こし、最悪の場合は過労死(karōshi)という悲劇的な結果をもたらすことがあります。
以上のように、職業病は時代とともに形を変えながら、依然として労働者の健康を脅かす重大な問題であり続けています。次の章では、具体的な職業病の種類とその症状について詳しく見ていきましょう。
代表的な職業病の種類と症状
職業病は多岐にわたりますが、業種や作業環境によって発症リスクが異なります。ここでは、業種別に代表的な職業病とその症状について解説します。
製造業・建設業における職業病
製造業や建設業では、物理的要因や化学物質による職業病が多く見られます。
じん肺

じん肺は、粉じんを長期間吸入することによって引き起こされる不可逆的な肺の線維化疾患です。特に鉱山労働者、溶接工、砂利採取作業者などに多く見られます。
主な症状:
- 慢性的な咳
- 呼吸困難
- 胸痛
- 疲労感
厚生労働省の統計によれば、2020年度のじん肺新規有所見者数は約200人で、累計では数万人に達するとされています。一度発症すると完治が難しく、予防が最も重要な疾患の一つです。
騒音性難聴
工場や建設現場など、長時間にわたる大きな騒音にさらされることで発症する聴覚障害です。
主な症状:
- 高音域から始まる聴力低下
- 耳鳴り
- 音の歪み
- コミュニケーション障害
| 騒音レベル | 許容される連続暴露時間 |
|---|---|
| 85 dB | 8時間 |
| 88 dB | 4時間 |
| 91 dB | 2時間 |
| 94 dB | 1時間 |
| 97 dB | 30分 |
オフィスワーカーに多い職業病
デスクワークが中心のオフィスワーカーにも、特有の職業病が存在します。
腰痛・頸肩腕障害
長時間の同一姿勢での作業や不適切な作業環境が原因で発症する筋骨格系の障害です。
主な症状:
- 慢性的な腰痛や首・肩の痛み
- しびれ感
- 運動制限
- 筋肉の硬直
日本整形外科学会の調査によると、職業性腰痛を経験したことがある労働者は全体の約70%に上るとされています。特にデスクワークと重量物の取り扱いを交互に行う職種ではリスクが高まります。
ドライアイ症候群
コンピューター作業による長時間の目の使用で、瞬きの回数が減少し、涙の蒸発が促進されることで起こる眼の疾患です。

主な症状:
- 目の乾燥感・異物感
- 目の疲れ・痛み
- 充血
- 視力の一時的な低下
医療従事者に特有の職業病
医療従事者は特有のリスクに直面しています。
感染症リスク
医療従事者は様々な感染症に曝露するリスクがあります。COVID-19パンデミック時には、医療従事者の感染率は一般人口の約3倍高かったというデータもあります。
主なリスク:
- ウイルス性肝炎
- 結核
- COVID-19などの呼吸器感染症
- 耐性菌感染症
ラテックスアレルギー
医療用手袋などに含まれるラテックス(天然ゴム)に対するアレルギー反応で、医療従事者の約10%が何らかの症状を経験しているとされています。
主な症状:
- 接触部位の発赤・かゆみ
- 鼻水・くしゃみ
- 喘息様症状
- 重症例ではアナフィラキシーショック
サービス業における職業病
接客業や飲食業などのサービス業にも特有の職業病があります。
声帯結節・ポリープ
教師、コールセンター従業員、歌手など、職業的に声を多用する人に見られる声帯の障害です。
主な症状:
- 声のかすれ
- 発声時の痛み
- 声域の狭小化
- 慢性的な喉の違和感
下肢静脈瘤
美容師、販売員、調理師など長時間立ち仕事を行う職業に多く見られる静脈の疾患です。
主な症状:
- 脚のむくみや重だるさ
- 静脈の浮き出し・こぶ
- 皮膚の変色
- 痛みやかゆみ

以上、各業種における代表的な職業病を紹介しましたが、これらは氷山の一角に過ぎません。次の章では、これらの職業病を予防するための対策と、発症した場合の対処法について詳しく解説します。
職業病の予防策と対処法
職業病は一度発症すると完全に回復することが難しい場合も多く、何よりも予防が重要です。また、早期発見・早期対処によって症状の進行を防ぐことも可能です。この章では、職業病を予防するための具体的な対策と、すでに症状が出ている場合の適切な対処法について解説します。
職場環境の改善
職業病予防の第一歩は、適切な職場環境の整備です。労働安全衛生法では、事業者に対して労働者の安全と健康を確保するための措置を講じることを義務付けています。
物理的環境の改善
具体的な改善策:
- 騒音対策: 防音壁の設置、騒音発生源の隔離、低騒音機器への更新
- 照明環境: 適切な明るさの確保、グレアの防止、自然光の活用
- 室内空気質: 適切な換気システムの設置、有害物質の排出管理
- 温度・湿度管理: 季節に応じた適切な室温・湿度の維持
これらの対策は比較的コストがかかるものの、長期的には労働者の健康維持や生産性向上につながります。日本産業衛生学会の調査によれば、適切な職場環境整備によって職業病の発生率が約30%減少したという報告もあります。
人間工学に基づいた作業環境の整備
特にオフィスワーカーに多い筋骨格系の職業病を予防するためには、人間工学(エルゴノミクス)に基づいた作業環境の整備が不可欠です。
重要なポイント:
- 作業台・椅子の高さ調整: 個人の体格に合わせた調整
- コンピューターディスプレイの位置: 目線より若干下に設置
- キーボード・マウスの配置: 肘が90度になる高さに設置
- 定期的な姿勢変換の推奨: 長時間同じ姿勢を続けないよう工夫
個人による予防対策
職場環境の改善と同時に、個人レベルでの予防対策も重要です。自分の健康は自分で守るという意識を持ち、以下のような対策を心がけましょう。
適切な保護具の使用
業種に応じた適切な保護具の使用は、職業病予防の基本です。
業種別の推奨保護具:
| 業種 | 推奨される保護具 |
|---|---|
| 建設業 | ヘルメット、安全靴、防じんマスク、耳栓 |
| 製造業 | 作業に応じた手袋、ゴーグル、防護服 |
| 医療従事者 | 使い捨て手袋、マスク、フェイスシールド |
| オフィスワーク | ブルーライトカットメガネ、リストレスト |
健康的な作業習慣の形成

効果的な習慣:
- 定期的な小休憩: 1時間に5-10分程度の休憩を取る
- ストレッチング: 特に使用頻度の高い筋肉のストレッチ
- 水分摂取: 適切な水分補給による体調管理
- 目の休息: 20-20-20ルール(20分ごとに、20フィート[約6m]先を20秒見る)
早期発見のための定期健康診断
職業病の多くは、初期症状が軽微であったり、一般的な疲労感と区別が難しかったりします。定期的な健康診断によって早期発見することが重要です。
法定健康診断と特殊健康診断
労働安全衛生法では、事業者に対して従業員の定期健康診断を実施することを義務付けています。特に有害業務に従事する労働者については、特殊健康診断の実施も義務付けられています。
主な特殊健康診断:
- じん肺健康診断
- 有機溶剤健康診断
- 騒音健康診断
- VDT作業従事者健康診断
- 腰痛健康診断
厚生労働省のデータによれば、特殊健康診断の受診率は約95%と高い水準にありますが、小規模事業所では実施率が低い傾向にあります。
職業病発症後の対処法
すでに職業病の症状が出ている場合は、以下のような対処が必要です。
医療機関の受診と治療
症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。特に職業病に詳しい産業医や労働衛生コンサルタントに相談することをお勧めします。
治療の流れ:
- 正確な診断: 症状と作業環境の詳細な聴取
- 治療計画の立案: 症状の緩和と進行防止
- 定期的なフォローアップ: 経過観察と治療効果の評価
- 職場復帰支援: 必要に応じた就業上の配慮
労災認定と補償
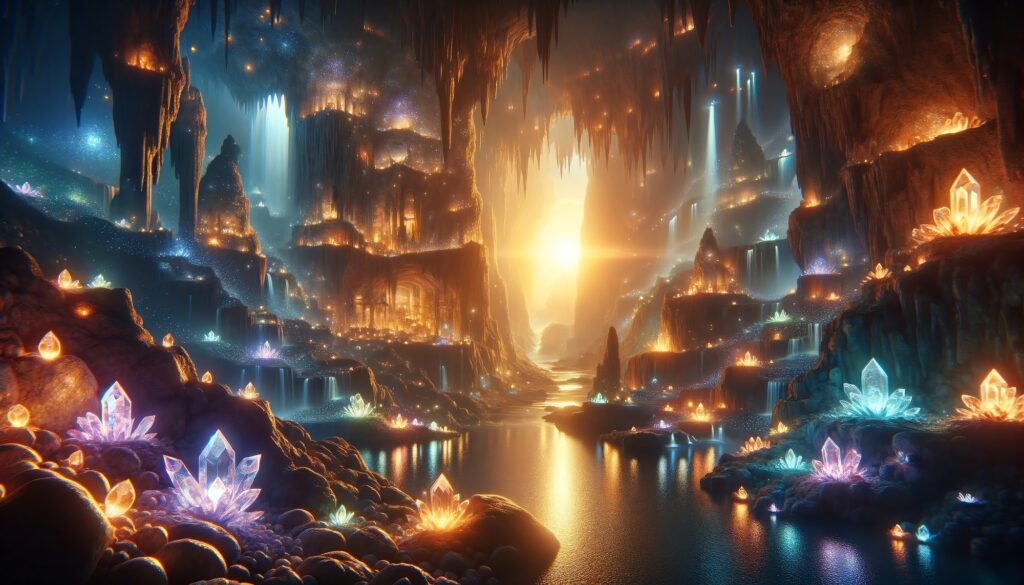
職業病が原因で休業や治療が必要になった場合は、労災保険による補償を受けることができます。
労災申請の流れ:
- 医師による「業務起因性」の証明
- 事業場を管轄する労働基準監督署への申請
- 調査・審査
- 認定・不認定の決定
労災認定されると、治療費の全額給付や休業補償(給与の約80%)など、手厚い保障が受けられます。しかし、職業病の労災認定率は疾病によって大きく異なり、例えば過労死の認定率は約30%程度とされています。
以上、職業病の予防策と対処法について解説しました。職業病は完全に防ぐことが難しい場合もありますが、適切な予防対策と早期対処によって、その影響を最小限に抑えることが可能です。何よりも重要なのは、労働者自身が自分の健康に関心を持ち、異変を感じたら早めに対処することです。
ピックアップ記事

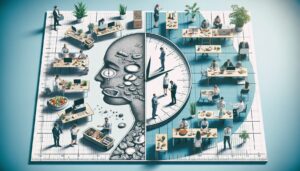
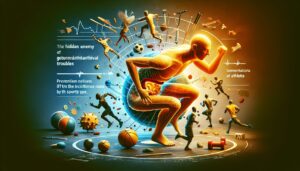


コメント